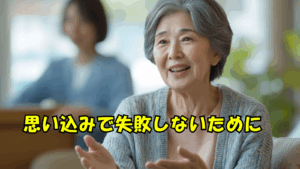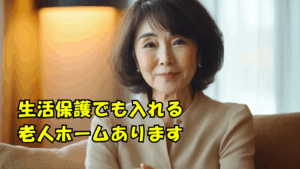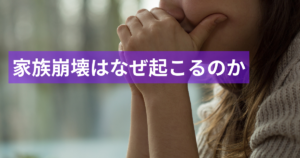はじめの一歩は地域包括支援センターに相談する
地域包括支援センターは、各市区町村に必ず設置されている公的な相談窓口であり、介護に関する「よろず相談所」のような存在です。
相談から施設選びまでの流れ
「親の介護が大変で、施設を考えていますが、どこから始めればいいか分かりません」とそのまま伝えれば大丈夫です。専門職(保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー)が丁寧に話を聞き、必要なステップを整理してくれます。
状態を詳しく聞き取った上で、要介護認定申請が必要なら一緒に進めてくれます。申請に必要な書類や流れも説明してくれるので、一人で悩む必要はありません。
親御さんの状態、家族の希望、経済状況などに合わせて、現実的な選択肢を一緒に考えてくれます。
多くの人は、「認定申請を自分でやらなければならない」「施設を自分で探して決めないといけない」と思い込み、心が重くなって動けなくなります。
でも、実際は 「まず相談するだけ」 でいいのです。
相談すると、気持ちが整理され、「次に何をすればいいか」が一つずつ見えてきます。誰かと一緒に進める感覚は、介護において極めて大事です。
地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、利用者の状況やニーズを踏まえた個別のケアプランを策定し、適切な介護サービスを提供するための調整や連携を行います。
センターには通常、以下の専門職が配置されます。
- 保健師または看護師(健康面の相談、予防活動)
- 社会福祉士(権利擁護、生活支援)
- 主任介護支援専門員(ケアマネジャーを指導・支援)
受けられるサポート(無料)
- 親御さんの状態を聞き取って、何から始めるべきか整理してくれる
- 要介護認定の申請のサポート(書類、主治医への依頼の説明)
- どの施設が合いそうかの具体的アドバイス
- 家庭でできるサービスとの比較
- 経済的な支援制度の紹介
地域包括支援センターは「何をすればいいのか分からない」という状態の人を、ゼロから伴走してくれる場所です。何から始めたら良いかわからない時はまず地域包括支援センターに相談しましょう。
介護施設にはどんな種類があるのかを把握する
介護施設は一言で「老人ホーム」とまとめられがちですが、実際にはその性質、目的、入所条件、サービス内容が大きく異なります。
また、すべての施設が「誰でも」「どんな状態でも」受け入れてくれるわけではないという現実があります。
- 特別養護老人ホーム(特養)
-
特養は常に介護が必要な高齢者が、生活の場として長期間入居するための公的施設です。「終の棲家」として利用されることが多く、食事、排泄、入浴などの介助、健康管理、レクリエーション活動などが提供されます。
入居条件
- 65歳以上で要介護3以上の認定を受けている方
- 40~64歳で特定疾病により要介護3以上の認定を受けている方
- 介護老人保健施設(老健)
-
老健は、在宅復帰を目的とした中間的施設です。病院での治療を終えた高齢者が、自宅に戻るために必要なリハビリや介護を受ける「つなぎ」の役割を担います。
入居条件
- 65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方
- 40~64歳で特定疾病により要介護認定を受けている方
- 病状が安定し、リハビリや在宅復帰を目指す方
入居は長期ではなく、3~6か月程度の利用が一般的。
- 有料老人ホーム
-
有料老人ホームは、民間企業が運営する施設で、介護や生活支援、食事サービスを含む住宅型施設です。「介護付き」「住宅型」「健康型」といった種類に分かれ、それぞれサービス内容が異なります。
施設区分 主な入居条件 介護付 65歳以上で要介護1以上 健康型 60歳以上、自立している方 住宅型 60歳~65歳以上が多 - サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
-
サ高住は、高齢者向けのバリアフリー賃貸住宅に、安否確認と生活相談サービスが付いた住宅です。「介護施設」ではなく、基本的には「住宅」と位置づけられます。
入居条件
- 年齢60歳以上の高齢者
- 60歳未満でも、要介護(要支援)認定を受けている方
- 自立~要介護5まで幅広い受け入れだが、施設により受け入れ体制が異なる
- 配偶者、60歳以上の親族等の同居も可
- 年齢60歳以上の高齢者
- ケアハウス
-
ケアハウスは、比較的自立している高齢者のための軽費老人ホームです。食事の提供や見守り、生活相談などの支援があり、一人暮らしが不安な高齢者が安心して暮らせるように設計されています。
入居条件
- 一般型
- 60歳以上の高齢者(夫婦の場合、一方が60歳以上なら同居可)
- 自立が難しいが、日常生活動作がある程度自力でできる人
- 介護型
- 65歳以上かつ要介護1以上
- 一般型
- グループホーム
-
グループホームは、認知症の高齢者が少人数(1ユニット9人以下)で共同生活を営む施設です。家庭的な雰囲気の中で、できることは自分で行いながら、認知症の進行を緩やかにすることを目的としています。
入居条件
- 65歳以上で、要支援2または要介護1以上の認定を受けている方
- 医師の診断による認知症の方
- 施設と同じ市区町村に住民票があること
以下の質問に回答すると最適な施設が見つかります。
月額10万円以下の老人ホーム

要介護認定の申請をする
なぜ要介護認定が必要なのか?
日本の介護保険制度は、「家族の負担を軽減し、社会全体で高齢者を支える」ことを目的に作られています。この制度を使うには、要介護認定という「公式の証明書」が必要です。
要介護認定を受けると、「要支援1・2」または「要介護1〜5」と段階的に分類され、その区分に応じて次のような公的サービスが利用できます。
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設入所
- デイサービス(通所介護)
- 訪問介護
- 福祉用具レンタル
- 住宅改修補助 など
要介護認定の「入口」を通らない限り、公的支援は一切利用できません。
要介護認定によって費用負担が軽減される
要介護認定を受けると、介護保険が適用され、サービス利用料の自己負担は原則1割(所得によって2割または3割)になります。
これがなければ、すべてのサービス費用を全額自己負担しなければならず、たとえば施設入居であれば月額30万〜50万円以上になる場合もあります。
要介護認定は、介護保険サービスを利用して費用負担を軽減するために必要な手続きです。
要介護認定が施設入所の条件になる
特別養護老人ホーム(特養)は要介護3以上が原則、グループホームは要支援2以上かつ認知症が条件など、施設には必ず入所条件があります。これを満たすためには、要介護認定の結果が必要です。
つまり、認定がなければそもそも申し込みができないという現実的な理由があります。
要介護認定はどこで受けられるのか
- 市区町村が窓口
-
要介護認定の申請は、親御さんが住民票を置いている市区町村の「介護保険担当窓口」で行います。
多くの場合、「福祉課」「介護保険課」などの名前がついています。
ここが申請書の提出先であり、調査の手配、主治医意見書の依頼、審査会の運営など、すべての事務手続きを行います。
- 地域包括支援センターで相談
-
初めての方にとって市役所に直接行くのは心理的ハードルが高いです。その場合は、地域包括支援センターが、申請をサポートしてくれます。
地域包括支援センターでは、
- 要介護認定申請の説明
- 書類の記入サポート
- 申請の提出代行
- 認定後のケアプラン相談
まで一括して支援してくれるので、最初にここに相談する人が多いです。
- ケアマネジャーによるサポート
-
すでに要介護認定を受けてサービスを利用している場合は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が再認定や区分変更申請を代わりに進めてくれる場合もあります。
「要支援1・2」「要介護1〜5」の特徴
介護サービスに使える支援制度
- 介護保険制度
- 高額介護サービス費制度
- 補足給付(特定入所者介護サービス費)
- 社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」
- 医療費控除(所得税)
- 住宅改修費の支給
- 障害者控除・特別障害者控除
支援制度と一言でいっても、実際には 介護保険制度を中心に、所得や資産状況に応じた多様な補助制度 があります。多くの家族が「費用が心配」と感じる一番の理由は、これらの制度の全体像が見えにくいからです。
ここでは、理論的に体系立てて、「何を目的に、どんな人が使えるか」という観点で解説します。
介護保険制度
日本では40歳以上の人が介護保険料を支払っており、要介護認定を受けた人は、この保険を使って介護サービスを利用できます。原則として、サービス利用料の 1割(所得に応じて2割または3割) を自己負担すればよい仕組みです。
- 具体的に使えるサービス
-
- 訪問介護(ヘルパー派遣)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具レンタル
- 住宅改修(手すり設置など)
- 特養、老健などの施設入所
- 対象者・条件
-
- 65歳以上(第1号被保険者)
- 40〜64歳の医療保険加入者で、特定疾病による介護が必要な方(第2号被保険者)
- 申請方法
-
お住まいの市区町村役所の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターにて申請。申請書と被保険者証、マイナンバーなどを提出。
高額介護サービス費制度
ひと月に支払った介護サービス利用料の自己負担合計が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
- 対象者・条件
-
介護保険サービスを利用している人で、自己負担額が一定額を超えた人。所得区分に応じて上限額が決まります。
- 申請方法
-
要介護・要支援認定を受けて介護保険サービスを利用し、自身・世帯の自己負担合計が上限額を超えた場合
高額介護サービス費とは!?知っておきたい払い戻し制度や申請方法(LIFULL介護)
補足給付(特定入所者介護サービス費)
特別養護老人ホームや老健などの施設に入所すると、介護保険によるサービス費用以外に、食費・居住費がかかります。この負担が重くなる低所得世帯に対しては、「補足給付」が支給されます。
- 対象者・条件
-
- 住民税非課税世帯
- 一定以下の年金・収入
- 預貯金が一定額以下(単身者:1,000,000円以下など)
- 申請方法
-
福祉施設を所管する市区町村役所(高齢者支援課・介護給付担当等)の窓口で直接申請。必要書類(預金通帳、保険証など)を持参。
特定入所者介護サービス費(介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度)とは(あずみ苑)
社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」
社会福祉協議会が実施している公的貸付制度で、介護保険サービスの利用料、施設入居の初期費用、住宅改修など、急にまとまったお金が必要になった場合に無利子または低利で借りられる制度です。
- 対象者・条件
-
- 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯(おおむね65歳以上)
- 他で借入困難な場合
- 申請方法
-
お住まいの市区町村社会福祉協議会窓口で申請。窓口で相談し、申請書・必要書類を提出。審査の上、貸付決定。
医療費控除(所得税)
介護費用の一部は、医療費控除の対象になります。
訪問介護や訪問看護、通院費用、特定の施設入所費(医療系施設など)など、一定の条件を満たせば、年間10万円(または所得の5%)を超えた医療費について、所得税や住民税の控除が受けられます。
対象になるかどうかは支払先や内容によって異なるため、領収書の保管と確認が大切です。
- 対象者・条件
-
医療費を支払った納税者本人や同一生計の配偶者・親族。
- 申請方法
-
住所地を管轄する税務署へ、確定申告時に申請(書類持参・郵送・電子申告いずれも可)。
必要書類:確定申告書・医療費控除明細書・領収書等
医療費控除とは?確定申告のやり方・計算方法についてわかりやすく解説(freee)
住宅改修費の支給
在宅介護を安全に続けるには、家の構造を変える必要がある場合があります。そのために、介護保険では住宅改修費用の一部(上限20万円)を支給する仕組みがあります。
- 対象者・条件
-
要支援・要介護認定を受け、自宅の介護保険対象の住宅改修を行う方。
- 申請方法
-
工事前に申請書を提出し、工事の見積書、ケアマネジャーが作成する理由書、改修前の写真を一緒に提出します。承認を受けた後に工事を実施し、終了後に工事後の写真や請求書を提出して費用の支給を受けます。
障害者控除・特別障害者控除
所得税・住民税の計算上、障害者控除や特別障害者控除を受けられる制度です。
- 対象者・条件
-
要介護認定を受け、日常生活に著しい制限がある人、認知症など判断能力が低下している人。
- 申請方法
-
- 会社員→勤務先へ年末調整の際に申請書類を提出。
- 個人申告または漏れがある場合→確定申告で税務署に申請。
証明書や障害者手帳等を添付